近年、コロナウイルスの再流行が繰り返される中で、介護施設は特に感染症のリスクが高い現場です。高齢者は重症化しやすいため、施設内で一度クラスターが発生すると、利用者の生命に直結する深刻な事態になりかねません。
そこで本記事では、介護現場で実践できる予防策と、実際に感染が発生した場合の具体的な対応策を、体験談を交えながら解説していきます。

体験談
私の介護仲間が勤める特養で、ある冬にコロナ感染が発生しました。
最初は職員の一人が「ちょっとした風邪かもしれない」と思いながら勤務してしまったのが始まり。翌日、数名の利用者に発熱が見られ、検査の結果コロナ陽性が判明。施設全体が緊張感に包まれました。
しかしその施設では、日頃から「ゾーニング」や「対応マニュアル」を作成していたため、感染者エリアと非感染者エリアを即座に分け、職員も班ごとに配置換え。結果、最小限の拡大で収束させることができたのです。
この体験は「日頃からの備えが命を守る」ということを改めて実感させてくれました。
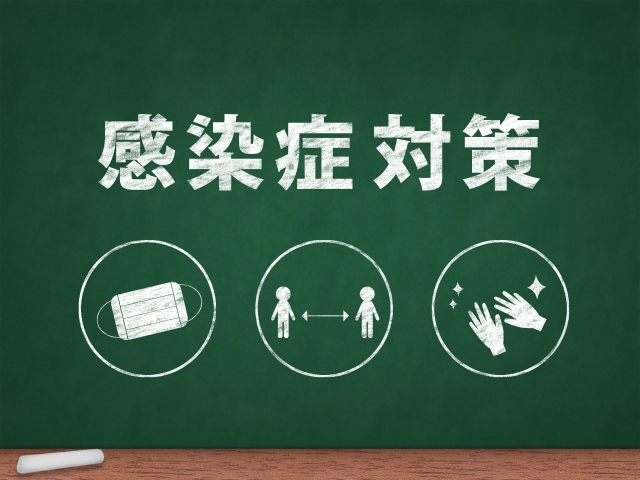
感染症を防ぐために介護施設でできる予防策
① 基本的な感染対策を徹底する
- 手洗い・うがい・マスク着用は習慣化
- 利用者・職員ともに「体調チェックシート」で毎日の健康観察
- 換気や空気清浄機の活用
② ゾーニング(区域分け)を行う
- 感染者エリアと非感染者エリアを明確に分ける
- 動線を交わらせないよう、看板や仕切りで工夫
③ 共有物の消毒を徹底
- テーブル・ドアノブ・手すりは定期的にアルコール消毒
- タオルは共用せず、ペーパータオルや個別タオルを導入
④ 職員同士の意識を高める
- 「少しでも体調が悪いときは休む」というルールを徹底
- 勤務交代や応援体制を整えておく
⑤ 利用者・家族への説明と協力依頼
- 面会制限やオンライン面会の導入
- 家族に「体調が悪い時の面会は控える」よう周知
感染が発生してしまった場合の対応マニュアル
① すぐに上司・施設長に報告し、行政機関へ連絡
→ 保健所や自治体の指導を仰ぐことで、迅速かつ正しい対応が可能になります。
② ゾーニングを強化し、感染者と非感染者を分ける
→ 陽性者のケアは専任スタッフが行い、他の職員と接触しないよう徹底。
③ 記録を残す
→ 誰がいつどの利用者と接触したか、細かく記録しておくことが再発防止に役立ちます。
④ 家族への情報共有
→ 利用者家族は不安を抱くため、状況を正直に伝えることが信頼につながります。
⑤ 職員のケアを忘れない
→ 心身の負担が大きいため、休憩を確保し、場合によっては外部の応援職員を依頼。
まとめ
介護現場でのコロナ感染症対策は、日常的な予防の積み重ねが最も大切です。感染が起きたときに慌てず対応できるよう、施設全体でルールを作り、職員一人ひとりが意識を持つことが求められます。
「介護は人を支える仕事」であると同時に、「働く人も守られるべき存在」です。私たち一人ひとりの行動が、利用者と自分自身の命を守ります。
あなたの転職をサポートする!おすすめ介護転職サイト
「暴言・暴力への対応がチームで統一されている安心な施設に転職したい」とお考えの方へ。以下の転職サイトは、施設の利用者さんの状況や職員体制といった内部情報に詳しいプロのエージェントが、あなたの希望に合った職場を見つけるためのサポートをしてくれます。
介護求人ラボ
豊富な介護求人情報と、地域密着型のサポートが強みです。暴言・暴力に対する施設の体制など、現場の具体的な状況を事前に確認してくれることが多いです。

パソナライフケア
大手人材サービス「パソナ」グループが運営。充実したサポート体制と、非公開求人の多さが魅力です。高待遇かつ安全管理体制が整った優良施設の求人が豊富です。

リニューケア(関西特化)
関西エリア(大阪、京都、兵庫など)に特化した転職サイトです。地域密着だからこそ、トラブル対応の評判など、現場のリアルな情報を把握しており、特に関西エリアで転職を考えている方におすすめです。

👉 仲間同士で気軽に情報交換や悩みを相談できる場所もあります!
オープンチャット「介護の心と体の休憩所」
https://line.me/ti/g2/Ok_CJ-N8hoHAPVLX816_Ybx4GIgfIckWPTtaLA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


